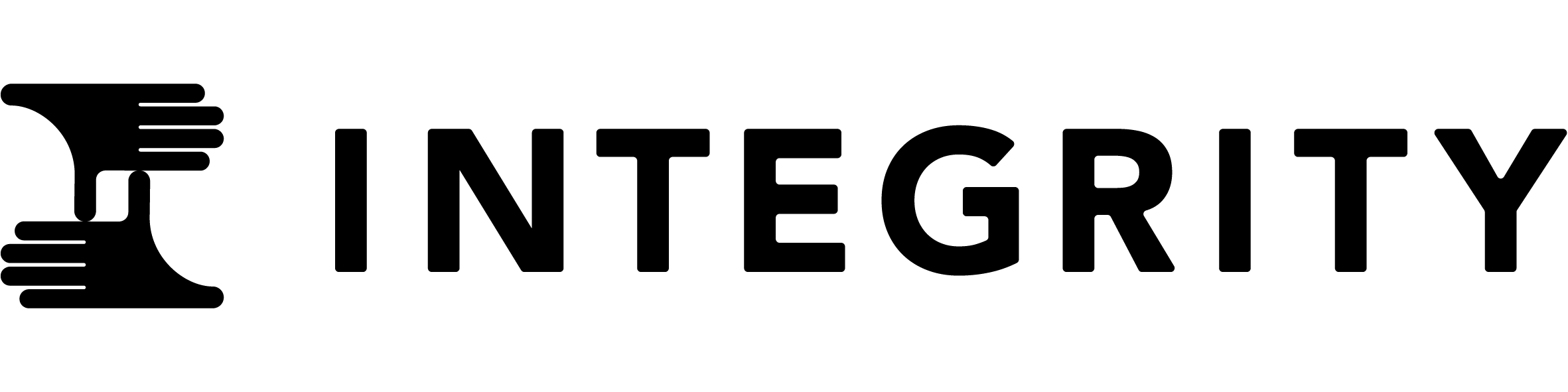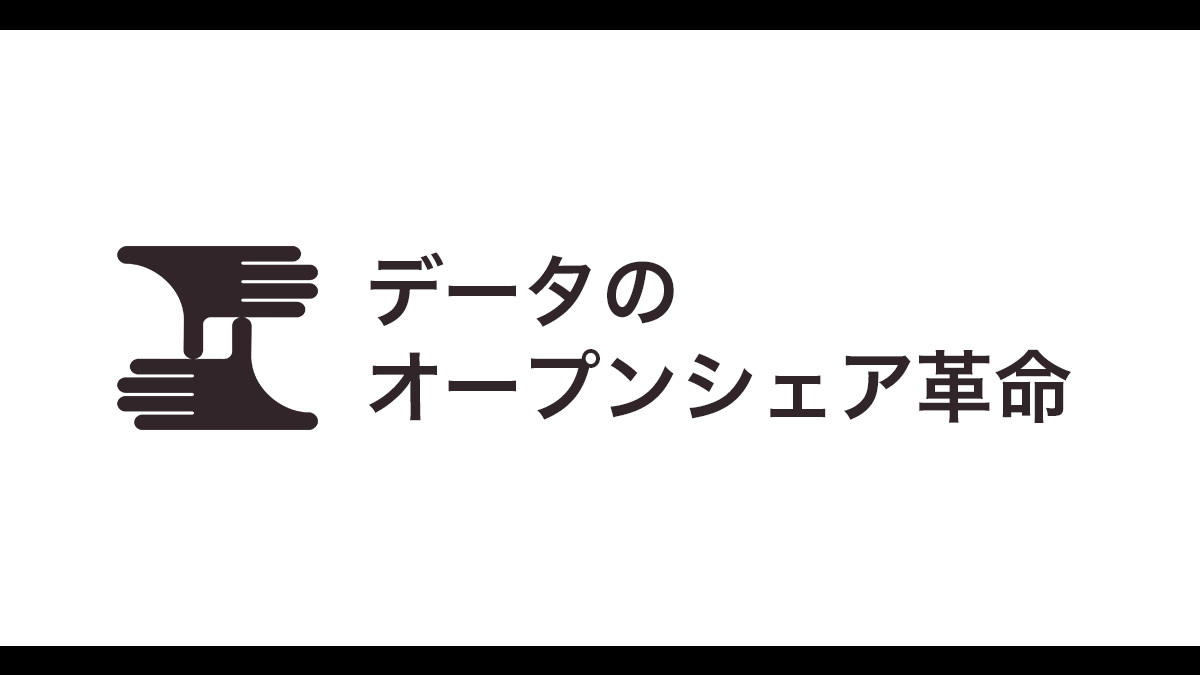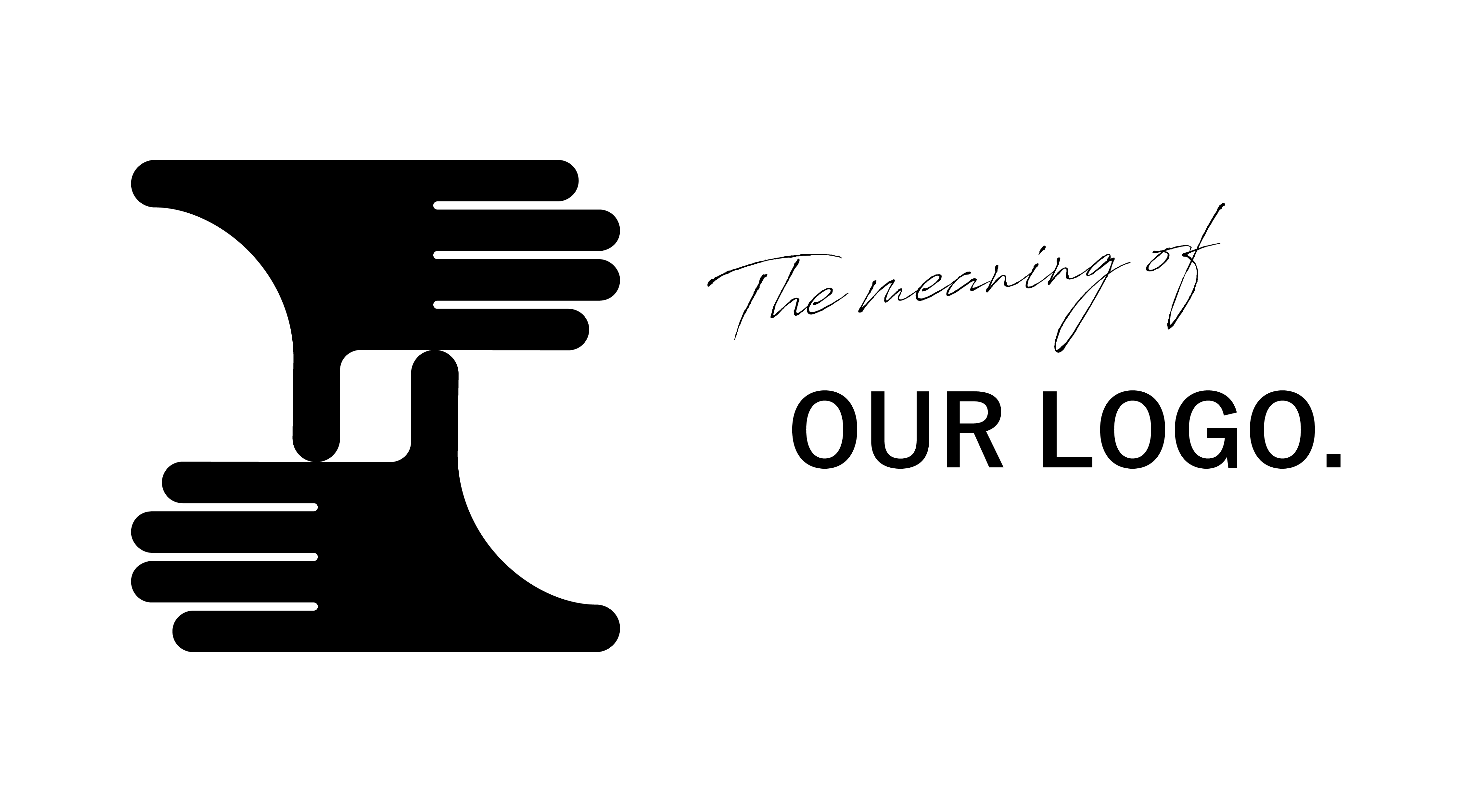講演を拝聴して…「SNSと生成AI時代に増大する偽情報問題と企業への示唆」
年代を問わず浸透した「SNS」。そして日々急速に進化を遂げる「生成AI」。この2つが組み合わさることで生じる、光と闇の「闇」の部分が非常に大きな問題だと、講演を拝聴して改めて実感をしました。
昨日、弊社が加盟する団体の名古屋商工会議所の講演に参加をしてきました。テーマは「SNSと生成AI時代に増大する偽情報問題と企業への示唆」。講師は第一生命経済研究所の柏村様で、プレゼンが上手であることもありますが、非常に興味深い、刺激が多い内容で、1時間超の講演があっという間に過ぎる感覚でした。
講演内容の中から特に印象に残った内容を共有させてください。
生成AIによる二次元情報の代替化と偽情報のリスク
適切な表現で言語化されて改めて実感したのですが、二次元における情報などは全て生成AIで代替できてしまう、という内容でした。
テーマの一つでもあるSNS。「X」や「TikTok」などは、まさに二次元における情報となり、これらの情報は全て生成AIで代替、すなわち生成AIで作れてしまうため、偽情報を判別することが、日を追う毎に難しくなる可能性があるということです。
三次元(リアル)で面識があるなど、特定のユーザーからの情報であれば真偽の判別も付きやすいかと思いますが、それ以外の情報については、偽情報かどうかも分からないほど自然な形で情報が流れてくるため、悪意なく、正しくない情報を拡散する手助けをする可能性も出てくるかと考えています。
ここで大事なポイントは、「生成AI」が人間と同じ自然な形で偽情報を作れることを「知っている」ことが重要だと言うことです。
日本人の多くが生成AIを使わないから、SNSなどで簡単に偽情報を信じ込み、それが拡散されてしまい、結果として経済損失などにつながる可能性があるとの指摘でした。
これはおっしゃる通りだと思いました。
もちろん偽情報を発信する人が悪い原因ではありますが、そういう人たちにアプローチをしても「イタチごっこ」であり、実質的に対策が難しいため、自分自身が知識を得て対策していく必要があると思います。
また兵庫県知事選などで散々な言われ方をしている「オールドメディア」(私自身は「オールド」という表現が好きではないのですが…)。「オールドメディア」の情報は、三次元であるリアルの人が情報を取りに行くため、そこでフィルターがかかり、一定の信頼性は担保できているメディアとなるため、そういう点では「生成AI」における偽情報の対策にはなるかと考えています。
※ただし「偏重した」報道はあると考えていますので、その判断能力は必要だと思います。
自身がAIを体験することが重要
もう本当にこれに尽きると思いました。特に有料プランに課金できていること。私もいくつか有料プランの生成AIを利用していますが、ここは先行投資だと思い、積極的に利用をしていくことが必要だと感じています。
商工会議所という団体の特性から中小企業の「経営者」が多いのですが、この経営者(私を含めて)が率先して生成AIを使わないと、この数年で明暗がハッキリと分かれると確信しています。
人間は自身が体験したことしか理解ができない生き物のため、情報収集などで生成AIのインプットをすることも大事ですが、まずは「生成AIを使う」という点を強く意識したいと思います。
生成AIの光と闇の部分である「光」は基本的に「生産性の向上」であると思いますが、「闇」の部分である「偽情報」「風評被害」などを対策できる力も付いてくると思います。
最後に:生成AI時代の危機意識と向き合う姿勢
まだまだ書き足りないのですが、本当に今回の講演を聞けてよかったと考えています。講師の柏村様が生命保険会社からキャリアをスタートされた背景もあり、日本人における「がん」になる確率(2人に1人)などの例えが秀逸でしたが、「自分には起こらないだろう」という謎の自信が本当に怖いなと思いました。
企業を経営する立場からすると生成AIを利用した「風評被害」などになりますが、生成AIができることを知り、実際に自身の会社に「風評被害」が起こることを認識すること。企業としては余計なコストがかかり、対応したくないのですが、誰もがアクセスできる生成AIで「風評被害」を簡単に作ることができる時代でもあるため、しっかりと向き合う必要があると考えています。